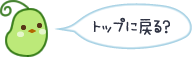12月になると喪中はがきが送られてくることがあります。喪中はがきを受け取ったら、「喪に服している相手」に対しての配慮で、こちらからは年賀状を送らないのが一般的です。こうした連絡をもらったとき、対応は2つ考えられます。
松の内(1月7日)が明けてから「寒中見舞い」を送る
暮れも押し迫った時期に喪中はがきが届き、年内に返事が出せない場合は松の内(1月7日)が明けてから立春の前の日(2月4日)ごろまでに「寒中見舞い」を送ると良いでしょう。喪中はがきに対する返礼も、既に弔問を済ませているならば改めてする必要はないとされていますが、喪主を気遣い、故人を悼む意味合いで、「寒中見舞い」を送ることが一般的です。但し、すでに弔問をすませているような場合には喪中はがきを受け取っても、あらためての返信は必要ないでしょう。寒中見舞いは、厳しい寒さのなか相手の安否を伺ったり、自分の近況などを書きます。年賀状は新年のお祝いの意味が込められているのに対し、寒中見舞いは年始の挨拶というより冬の最も寒い時期に書くお便りですので、喪中の方へのご挨拶にも利用されています。
この場合の挨拶状も華やかな装飾は避けて、お祝いの報告や遊びの話も控えましょう。結婚報告、出産報告などは喪中の返礼としてではなく、別のお便りとして送るのが好ましいでしょう。
年内に喪中はがきを受け取った旨の返事を出す
年内に返事を出すのであれば、できる限り速やかに送りましょう。時候の挨拶は必要ありません。まずはじめに、亡くなったことを知らなかったことをお詫びします。悲報を知った驚きから手紙をはじめ、ご遺族の今後や体調を気遣う言葉で結びます。
封筒や便箋は白を選んで置いたほうが無難でしょう。もちろん白いものでも、華美でないシンプルなものにしておきましょう。
年賀状を出してから喪中はがきが届いたら
出してしまった年賀状は仕方がありませんので、そういう場合は喪中はがきが届いた時点で「お悔み状」を出すのがマナーです。これは「訃報を知らずに年賀状を出してしまい、すみません」というもので、これを出せば、先に年賀状を出してしまっても問題ありません。お詫びと、故人のご冥福を祈る言葉を書きましょう。