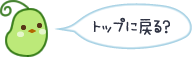喪中欠礼はがきには、出すタイミングや内容など、気をつけなければならない事がいくつかあります。ここでは喪中・年賀欠礼状の書き方についてご紹介します。
喪中はがきを出すタイミング
喪中・年賀欠礼状を出す理由は「年始の挨拶ができない」「年賀状の交換ができない」という旨を伝えるものです。送る相手が年賀状の準備を始める時期に間に合うように、11月中旬から12月上旬には届くように準備しましょう。年末に不幸があった場合には、すでに年賀状の準備を終えている、ないしは投函してしまっている場合もある為、寒中見舞いとして送るようにしましょう。喪中はがきの意味は、「喪に服しており新年のお祝いを控えていますので、こちらからのご挨拶は遠慮させていただきます」というお詫び状であって、先方からのご挨拶を拒否しますということではありません。
- 誰が、いつ亡くなったのか伝え、そのために現在自分が自分が喪中である(=喪に服している)事を伝える
- 自分が喪中である(=喪に服している)ため、年賀状を遠慮する旨を伝える
- 年始状に代わる挨拶(日頃お世話になっているお礼、先方の無事を祈る言葉、新しい年のお付き合いや支援をお願いする言葉など)
- 日付(例:平成◯年◯月◯日と記載して、西暦は用いない)
- 相手の名前と差出人名(家族は連名で出して構わない)
などの内容を明記して送付することになります。
喪中はがきを書く際の注意点
- 「賀」などの一般的におめでたい事を表現する言葉の使用は避けるのがマナーなので、文中に「年賀」は使わず「年始」「年頭」「新年」としましょう
- 頭語・結語は不要です。例えば「拝啓」で書き出し、「敬具」で結ぶといった体裁は不要です
- 葬儀の際のお礼など一言コメントを添える事は非常識ではありません。但し祝い事の報告を兼ねたり、砕けた内容の文章を記載する事は控えましょう。
- 改まった相手への喪中はがきでは、「。」「、」など句読点は使わないようにしましょう