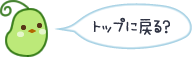「忌中」と「喪中」について
忌中
亡くなった日から忌明け(四十九日)までを「忌中」と言い、葬家は身を慎む期間とされています。昔は、忌中期間は家に閉じこもり身を慎んでいましたが、近年では職場などで決められた忌引期間に従って仕事に復帰したり、通常の生活に戻る人が多いようです。
喪中
「喪中」の「喪」とは、本来は近親者の逝去に伴い一定期間喪服を着用して故人の冥福を祈って慎ましく生活を送ることをいい、「喪中」とはその喪に服する期間(服喪期間)を言います。一般的に、故人が亡くなってから一年間(13カ月)を喪中期間と言います。
また、喪中は、忌中を含めて、通念上は一周忌までを指します。喪中はがきは、「今年は服喪期間なので年賀状を控えます」という年賀欠礼の挨拶状で、毎年年賀状を差し上げている方に前もって送ります。このように喪中である旨を伝え欠礼を詫びる書状を出すことが、現在では社会的習慣となっています。
明治時代の初期に発布された「服忌令」に定めた「服喪期間」の内の父母の13ヶ月(向う一ヶ年)が起源になっており、現在では一周忌(死去一年後)までの一年間を喪中とするのが一般的です。つまり、少なくとも両親が亡くなった場合には、それが何月であっても新年は喪中であるということになるのです。服喪は、最長50日で充分です。その後は神様となりご先祖となった祖霊を常にお祀りする心構えの方が大切です。いつまでも服喪を続けるよりも、新たに神様・仏様になられた故人の霊を、他の神仏と一緒に清々しくお迎えする方が、日本人にとって自然な新年の姿だと思います。
| 故人の続柄 | 忌日数 | 服喪日数 |
|---|---|---|
| 父母 | 50日 | 13ヶ月 |
| 養父母 | 30日 | 150日 |
| 夫 | 50日 | 13ヶ月 |
| 妻 | 20日 | 90日 |
| 嫡子(息子) | 20日 | 90日 |
| その他の子(娘) | 10日 | 90日 |
| 養子 | 10日 | 30日 |
| 兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |
| 祖父母(父方) | 30日 | 150日 |
| 祖父母(母方) | 30日 | 90日 |
| 叔父・叔母 | 20日 | 90日 |
| 夫の父母 | 30日 | 150日 |
| 妻の父母 | なし | なし |
| 曾祖父母 | 20日 | 90日 |
忌明け以降は、喪中の期間であってもお祝い事の参加は差し支えありませんが、自分の側からお祝い事を主催するのは控えましょう。また、喪中に迎えたお正月は、飾り付け・初詣・年始まわり・年賀状など、お正月の行事は控えます。
喪中はがきを出す相手の範囲
喪中・年賀欠礼状は、毎年年賀状のやり取りをしている方全員に11月末頃までに出しましょう。文面には、誰(差し出し人との続柄)の喪に服しているのか、いつ亡くなったのかを書き入れましょう。
相手も喪中で、こちらより先に喪中・年賀欠礼状を頂いた方にも忘れずに出しましょう。
喪中に年賀状をいただいたら、松の内(1月7日)が過ぎてから、年賀状のお礼と、喪中につき欠礼した旨を書いて返事を出します。
その他、仕事上のお付き合いで故人と面識がない方には、喪中・年賀欠礼状を出さずに年賀状を送っても構いません。故人と喪中・年賀欠礼状を送る相手との関係や、自分の気持ちを優先して考えたら良いのではないでしょうか。